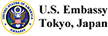TOMODACHI Alumni Highlight Series – 脇山輝衣菜氏

脇山輝衣菜氏は、東京大学先端科学技術研究センター社会包摂システム分野で障害や病気のある若者を対象としたリーダーシッププログラム「DO-IT Japan」の運営を行っています。多様な特性やニーズを持った人たちが社会の中で自分らしく生きる権利を擁護し、やりたいことに挑戦するための過程を伴走することに熱意を持っています。
自身も高校生の頃に神経の難病を発症し、進学や就労、さまざまな社会参加の機会で社会的障壁に直面してきました。障害とともに生きることのリアリティに対する共感や理解が少しでも広がることを願い、2022年のTOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilitiesのプログラムに参加しました。
TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities に参加した経緯について教えてください。
私が「TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities」に参加したのは2022年、大学在学中のことでした。高校2年生のときに神経系の難病を経験したことをきっかけに、障害や病気のある人々を取り巻く社会環境に関心を持つようになり、大学でもその分野を中心に学び・研究していました。
大学生活の中で、以前から海外に挑戦してみたいという思いもあり、TOMODACHIのプログラムに関心を持ちました。当初はボストンでの研修プログラムに応募する予定でしたが、コロナ禍の影響で「Story Jam」へと切り替わりました。もともとボストン研修に参加していた知人がいたこともあり、この機会にStory Jamに参加してみようと考えたのが、参加の経緯です。
参加されたTOMODACHIプログラムで、今でも思い返す特別な思い出はありますか?
Story Jamはオンラインで実施されたプログラムで、コロナ禍で移動や対面交流が制限されていました。ただ、そのような中でも物理的な距離を乗り越え、「障害」という共通のテーマを持つ参加者同士が集い、つながりを感じながら学び合えたことが強く印象に残っています。
TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities での経験は、脇山氏自身の成長にどのような影響を与えたと思いますか?
Story Jamを通じて初めて、自身の経験を「ストーリー」として語るストーリーテリングに挑戦しました。過去を振り返り、現在直面している課題と向き合う作業は決して容易ではありませんでしたが、自分の心に耳を傾け、これまで言葉にせず飲み込んできた思いを編み直していく過程は、「これからどのような未来を生きていきたいのか」を考える大きなきっかけとなりました。
また、他の参加者のストーリーに触れる中で、それぞれの経験から生まれる言葉や声は、飾り気がなくとも力強く、まっすぐ人に届くものだと強く感じました。自分自身を見つめ直すと同時に他者の声に耳を傾けることで、「自分の当たり前が必ずしも正しいとは限らない」という気づきを得ることができました。この経験は、他者と関わる際に、より柔軟な思考と寛容な心を持って向き合いたいと考えるようになる、重要な転機だったと思います。
現在携わっている「DO-IT Japan」でのお仕事について教えてください。
現在は、東京大学先端科学技術研究センター社会包摂システム分野で、障害や病気のある子どもや若者を対象としたリーダーシッププログラム「DO-IT Japan」の運営に関わっています。このプログラムでは、特にテクノロジーの活用に焦点を当てながら、参加者一人ひとりが自分のニーズに合った学び方や働き方を見つけられるよう支援しています。
また、そうした個々の取り組みを通じて、社会の中にどのようにインクルーシブな環境を広げていけるのかを参加者とともに考え、実践していくことも、重要な活動の一つです。
職業としてこの分野に携わるようになってから、自らの問題意識や課題意識が増えたり、変わったりしたものはありますか?
日本では障害のある人の権利に関する法制度が近年大きく整備され、多様な特性やニーズを持つ人を取り巻く環境が急速に変化していると実感するようになりました。一方で、日々のプロジェクトを通じて出会う中高生や大学生、就労を目指す若者、そして彼らが属する学校や職場を見ていくと、障害のある人を受け入れる側の知識やノウハウには、依然として大きなばらつきがあると感じています。
もともと私自身が強い関心を持っていたのは、障害のある人に向けられる社会のまなざしや、「社会の多数派とは違う存在」として捉えられてしまう構造でした。TOMODACHIでの経験を通じて、法制度や学校、企業、社会が果たすべき責任があることは前提としつつも、何より大切なのは一人ひとりの声であり、その声こそが最も真実に近いものだと考えるようになりました。
個々のストーリーから新たな共感が生まれ、当事者とそれぞれの環境との間で少しずつ「その人なりの正解」が形づくられていく——そのプロセスを支える手段として、私が関わる領域では、ストーリーテリングが今後も大きなブレイクスルーとなり得ると感じています。
昨年夏に参加された「INDEX(International Youth Development Exchange)」について教えてください。
INDEX(International Youth Development Exchange Program)は、日本政府が実施する国際交流プログラムで、私は日本の若者代表の一人として、他の7名の参加者とともにフランスを訪問しました。現地では、パリ2024オリンピック・パラリンピックに向けて新設・改修された施設を中心に、都市や公共空間のアクセシビリティについて視察を行いました。Disability Inclusionの分野で活動する中で、アクセシビリティは以前から強い関心を持ってきたテーマであり、このプログラムへの参加を決めました。
プログラムでは、東京2020とパリ2024という二つの大会が残したレガシーをもとに、バリアフリーやユニバーサルデザインの発展に向けた知見や課題について意見交換を行いました。中でも特に印象に残ったのが、パリで進められている都市計画の取り組みである「QAA」です。アクセシビリティ向上を重点的に進めるモデル地区では、公共施設のバリアフリー化が進んでいるだけでなく、誰にとっても分かりやすい案内表示が整備されていました。
さらに、物理的で目に見える整備にとどまらず、地域住民の多様性に対する寛容さや、支援を必要とする人に対してためらいなく手を差し伸べる姿勢にも、大きな刺激を受けました。
こうした経験を通じて、今後は次世代のグローバルリーダーとして、バリアフリーやユニバーサルデザインのさらなる発展に貢献していきたいと強く感じています。
今後数年、もしくは10年先の未来を見据えて、何か夢や目標などがあれば教えてください。
大学時代から自身の経験に関わる分野を学び、現在も障害や病気のある人たちに関わる仕事を続けている背景には、これまでの人生の中で、何度も納得のいかない経験をしてきたという思いがあります。将来の社会を考えたとき、障害のある人も、他の人と同じように選択肢やチャンスを当たり前に得られる環境が広がってほしいと強く願っています。
その実現に向けて、自分自身の経験を、自分を必要としてくれる誰かのためにどう活かせるのかを問い続けながら、役割や働き方を模索していきたいと考えています。同時に、自分自身も成長し続けられる環境に身を置きながら、長い視点で社会に関わっていくことが、今後の目標です。
最後に、自身も障害と向き合っていたり、この分野ついてもっと学びたいと考える若者に向けて何かメッセージを頂きたいです。
障害や病気と一言で言っても、その経験は一人ひとりまったく異なり、誰もがそれぞれに特別なストーリーを持っていると思います。近年は前向きな言葉や考え方も増えてきましたが、今なお苦しい壁に直面している人が多いのも事実です。私が、障害や病気と向き合う人たちに最も伝えたいのは、「あなたにとっての障害や病気の意味付けは、あなただけがしていいものだ」ということです。良い・悪い、ポジティブ・ネガティブといった評価を、他人に押し付けられる必要はありません。
また、Disability Inclusionの分野を目指す若者にとって、この領域は混沌としていて難しさを感じる場面も多いと思います。しかしその分、真摯に向き合う価値のある世界でもあります。さまざまなきっかけや問題意識を持つ人たちが集い、対話を重ねることで、学び合えるネットワークがこれからも広がっていくことを願っています。
近年、露骨な差別は減ってきていると感じる一方で、「障害のある人とどう接してよいかわからない」という戸惑いから生まれる心の距離は、まだ社会の中に多く存在しています。「障害」という言葉は緊張感を伴って受け取られがちですが、障害の有無ではなく、「わたしとあなた」「自分と相手」という関係性として向き合い、互いを尊重しながら、知らないことを素直に学び合い、共感し合うことが大切だと思います。そうした関係性が一つひとつ育まれていくことで、障害に限らず、個々の「自分らしさ」を理解し合える社会がつくられていくのではないでしょうか。
このインタビューは2025年12月23日に大澤和紘によって実施され、記事にされました。彼は現在TOMODACHIアラムナイ・プログラムのインターンです。