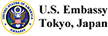プログラム参加者・TOMODACHIアラムナイに聞いてみました!:今井けい氏

今月のアラムナイハイライトは、今井けい氏をインタビューしました。今井氏はTOMODACHI Disaster Resilience Leadership Training Programのアラムナイで、現在、東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学研究室と、岡山大学ヘルスシステム統合科学研究課看護科学分野で研究員をしています。病院では救命救急センターで看護師として努めています。今井氏は数々の経験を通し、救急とIntensive Careという二つの柱を持ちながら活動しています。また、今井氏が日本集中治療医学会で発表した研究発表が二位を受賞し、長期間の研究期間を通して得た発見や気付きを今後の目標に繋げて行きたいと考えています。
どうして看護の道に進もうと思いましたか?
大学に入った時には看護の道に進もうとは全く思っていなくて、どちらかと言うと公衆衛生と言われるような領域に関心がありました。それをやるために法律とか違う学問を学んでいれば良かったんですが、多少は医療の知識を持っていた方がいいと思っていました。医療系の大学って色々あるんですが、その中で4年間で卒業ができ、修士課程を含めても6年間で終わると考えた時に公衆衛生の道に進みやすいと思ったので、上智大学の看護学科に進みました。全く看護の道に進もうと思ってなかったのが最初でした。なので最初は授業の内容が分からなかったり、面白くなかったりして、なかなか難しいと思っていました。僕がとある大学病院の救命救急センターのトレーニングに行った時に凄く重症な患者さんとお会いして、その人に「人間としてどういうことが出来るのか」という答えがうまく自分なりに見つけることが出来なかったので、そう言うものがわかるまでちょっとだけ看護の道を歩んでもいいのかなと思って公衆衛生ではなく看護の道に進もうと思いました。
実際看護の道に進まれて苦労を感じた経験を教えてください。
苦労という意味で言うと私が社会人2年目の時にウイルスが世界的に大流行して、その時にコロナ病棟を作ってくださいと言われました。僕がTOMODACHI イニシアチブのアラムナイとして何回か災害のボランティアに行ったことがあり、TOMODACHI DRT (Disaster Resillience Leadership Training Program)というプログラムで、岡山、熊本、そして福岡を訪れて、そこでプログラムに参加た経験から、コロナ病棟を新しく作るのを一緒にやってくれないかと言われました。そこで病棟を作ったり、マニュアルを作ったり、病院の職員に教えたりする仕事を始めました。病棟を作った時は大変だったなと思いました。しかも、『良くなったですね』と言えるようになる人はそれほど多くなく、私が普段働いているのは救急とか、クリティカルケア看護という領域で、そこに来るような人たちって歩いて帰れるようになって元気になって帰れる人も勿論いるんですが、全員がそういうわけではないんです。治療しても良くならなかったり、どんなに頑張っても良くならなかったり、その中ですごい苦しみながら生きていることがあったなと今でも思い出しますね。
何がきっかけで意思決定/心理ケアの方に興味を持つようになりましたか?
僕が普段働いている救急・集中治療は、必ずしも全員が良くなって幸せな気持ちになって退院していくわけではないんですね。どちらかというと今までできたことができなくなってしまったり、ご飯が食べれたのにご飯が食べれなくなったり、あるいは予期せず死んでしまったりとか、そうやって退院していく人たちも大勢いらっしゃるんですね。医療のこととか生きる死ぬとか、そういうことを考えてきたわけじゃない人たちが、突然そういう状況に陥ってしまいます。でも、そんな簡単に人って死なないわけですよね。だんだんいろんな治療がきかなくなったりとか、いろいろ具合が悪くなって良くなったり悪くなったりを繰り返して最終的には亡くなっていったり。その時には家族も傷つくし、あとは自分で飲んだり食べたり、歩いたりできた人が足を失ってしまったりとか、今までできたことができなくなるってことはすごくその人たちにとって辛いことです。そういう人たちとたくさん出会ってきたので、そのような領域をちょっと勉強して少しでも役に立てればいいのかなと思ったりしていました。
TOMODACHI DRT(Disaster Resillience Leadership Training Program)での経験を通して、今の道に進もうと思ったきっかけを教えてください。
TOMODACHI全体を通してですが、2013年に初めてTOMODACHIイニシアチブ のプログラムに参加しました。当時はまだ高校生で、僕は東北にゆかりがなく東京で生まれて横浜で育った人だったので、遠くのことは何も知らない。でもニュースですごい大変なことが起きていて、人間の力ではどうしようもないことってたくさんあるんだなっていうことですごく傷ついた時がありました。僕がその時に横浜市からアメリカに行くっていう経験をしたんですけど、それがTOMODACHIに最初に関わった時でした。ただ最初はアラムナイプログラムっていうものがなかったんですよ。なぜなら、アラムナイがほとんどいなかったからです。時間が経って2014年とかにはアラムナイが何人かたくさん集まってきて、アラムナイ向けのプログラムというのができるようになってきました。そこで会ったTOMODACHIの仲間たちって言うのが福島県とか宮城県とか岩手県のいわゆる本当に津波とか地震で家族が亡くなってしまったりとか、自分自身も被害を被ったりとか、原子力発電所の事故で関東地方に逃げてこざるを得なかった人たちとか、そういう人たちとたくさん出会ってやっぱり災害ってすごい身近なもので、こんなに近くに災害というものがあるんだっていうことをまず実感しました。そこで災害のこととかを勉強して、災害が起きた時には何か力になれればなっていうことを思ったりしていました。

集中治療医学会で発表した論文の研究内容を教えてください。
集中治療室に入った患者さんは「せん妄」っていう状態になることがあります。せん妄になった患者さんは、幻覚を見たりとか鬱になってしまったり、あとはになったりします。あとは認知機能が下がってしまったり、例えば簡単な計算とかが難しくなることもあります。あとは仕事でいろいろ口で言われたことが覚えられなくなってすぐに忘れてしまったり、そういうような状況になってしまう原因がせん妄って言われています。せん妄はいろいろなことをすれば予防することができるということがわかっていいます。しかし、せん妄はどの患者さんに起きるかがわからないんですよ。未来のことは私達にはわからないので、私は人工知能を使って集中治療室で治療を受けている患者さんも誰にせん妄が起きるのかっていうのを見つけるプログラムを作ろうと思って、それでそのプログラムを作りました。
論文を作成するに当たって、苦労などありましたか?
よくプログラムを作ったりするのが大変でしょ?って言われるんですよ。でも多分研究とかのほとんどって、多分そこが一番大変じゃないんです。看護師として働いたりとかして、多分全部の仕事に共通していることだと思いますけど、事前の準備が一番大変なんです。例えば、私の場合はプログラムをPythonっていうプログラムで作って自分で書いて、もちろん勉強して大変だったんですけど、それよりも大変だったのは、そのPythonのプログラムを入れるデータを取ったりとか、どれが正しくてどれが間違ってるのかな?とか、ちゃんと自分で精査をしたりしてそのデータがしっかり作れないといけないんです。なので、そのデータを取るための時間が80%ぐらいで、残りの10%で論文を書いていました。
これから看護の道に進みたい方へメッセージはありますか?
自分をよく知ることが大事かなと思います。なぜかというと、自分のことを知らないと、自分にとってのこれが正しい、これがいいだろうっていうことを患者さんに押し付けてしまうので自分の価値観とか何を大事にしているかっていうものをちゃんとわかっていないと後々誰かを傷つけてしまいます。まず、自分のことを知ることはとても大事だと思います。あともう一つは色々な経験をしてください、ということです。なぜかというと、人間が生きてる時間って病院に行ったりとか、医療が必要になる時は凄くわずかです。何年も入院している人はいますけど、病気のことを考えたりする時間よりも家族とか友達と過ごしたりする時間の方が長いはずなんですよ。なので、医療のこととか看護のこととかを真面目に勉強するのは大事なんですけど、普段会わないような人、いろんな経験を積んでいろんな人の意見を知ることによって、生活をしている中で、普段生きている中で突然医療が必要になってしまった人たちのこともよくわかるようになるので、ぜひそのいろいろな経験を積むっていうのは大事なんじゃないかなと思ったりしています。
これからの目標を教えてください。
集中治療後症候群(PICS: Post Intensive Care Syndrome)っていうものがあります。集中治療室に入ったりとか、救急の現場に来る患者さんっていうのはもちろん良くなる人もいるんです。でも、集中治療室に入ったりとか、そこで治療を受けるということによっていろいろ苦しいことがあり、さっき言ったせん妄とかにもなってしまうわけです。そういう集中治療室に入った患者さんに起きるのを集中治療後症候群(PICS)って言ったりするんですね。PICSをなくしたいっていうのが僕のこれからの目標になります。せっかく良くなって元の生活を取り戻すために集中治療室に頑張って入って治療を受けたのに、集中治療室に入ったことが原因でPICSになるっていうのはすごく辛い。命が助かることはもちろん大事なんですけど、そのために来てるわけじゃないですよね。僕たちはハッピーでちゃんと自分で歩いたりとかおいしいご飯をちゃんと食べて、家族と楽しい時間を過ごせて、苦しいトラウマとかに苦しめられ続けるようなPTSDのような症状がなく、平和に過ごしていけたら一番いいですよね。命が助かればいいじゃないかって思われていた。その救急とか集中治療の中では今まであまり顧みられてこなかった。でも、今、医療が進歩して集中治療を受けて救急で救命されて、ちゃんと生きて退院できる人が増えてきました。でも、増えたということは、PICSで苦しむ人も増えているというわけです。なので、今まではそのPICSというものにあまり目を向けられてはこなかった状況があるんです。ピックスに関して原因を少し調べてみたりとか、どうしたら予防ができたりとか少なくなるのかっていうことを研究したい。その研究のためには、自分で研究する力をつけたりとかする必要があるので、大学院でちゃんと勉強して研究をして社会の役に立てるような研究をこれからもやっていきたいなというのがこれからの目標になります。
このアラムナイ・ハイライト・インタビューは、2025年4月9日に高波爾奈によって行われた。高波氏は現在、TOMODACHIアラムナイ・リーダーシップ・プログラムのアラムナイインターンです。