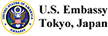プログラム参加者・TOMODACHIアラムナイに聞いてみました!:佐藤輝氏

4月のアラムナイ・ハイライトは、TOMODACHIサマーコカ・コーラホームステイ研修プログラムのアラムナイである佐藤輝氏さんにスポットを当てました。このプログラムは、2011年3月11日の東日本大震災で被災した高校生に、アメリカでの文化交流の機会を提供するものである。佐藤氏は現在、ロンドンのセントラル・セント・マーティン芸術大学でNarrative Environmentというプログラムの修士課程に在籍しています。TOMODACHIプログラムに参加した後、佐藤輝氏は音楽と若者のクラブシーンに焦点を当てたソーシャルメディアを通じて、若者同士がファッション、音楽、興味を披露し合うだけでなく、社会的、政治的な意識を持ち、互いに議論する安全な空間を持つためのアンダーグラウンド・ムーブメントを始めました。
今日は大学生活でとても重要だった経験の一つ、TOMODACHIの話をしたいと思います。
TOMODACHIとは、東日本大震災の復興支援をきっかけに発足した官民パートナーシップのことです。僕は高校1年生の時に、Coca-Cola社とTOMODACHIによる3週間のアメリカ短期留学プログラムに参加しました。他にもソフトバンクやMUFGなど、名だたる民間企業との別プログラムも複数存在しています。それぞれのプロジェクトの参加者がアラムナイ(=同窓生)という形で交流する機会がその後もたくさんあり、確か大学3年生くらいまでは積極的にこの活動に関わっていました。

TOMODACHIサマーコカ・コーラホームステイ研修プログラム
僕が大学生になった2016年には、そのアラムナイの規模が全国に大体7000人ぐらいまで拡大していたそうです。そこで全国でアラムナイのネットワーキングの旗振り役を設けるプロジェクトが発足し、ご縁もあって東北地方のリーダーの1人に選んでいただきました。これは高校生と大学生がそれぞれ合計10人くらい選出されペアになり、そこに社会人メンターが付くというもので、今でも信じられないくらい優秀な人たちが揃っていました。特に高校生。「フレームワークを使ってイシューを可視化し、タスクを洗い出して〜」みたいな会話を理解して行動に移せるんです。しかも英語で。アイツらなんだったの?という気持ちでした。

TOMODACHIアラムナイ地域フレームワーク
当時の僕はほとんど英語が話せませんでしたが、英語以前にマジで何もわかりませんでした。(分からなすぎてプルデンシャル本社の高層階で泣いた。)さすがにこれには喰らいました。TOMODACHI関連のプロジェクトに関わって、なんとなく自分も優秀な人の仲間入りをしてたつもりでしたが、実力不足をフットワークの軽さで誤魔化していたことにやっと気がついたようです。

After I cried
今思っても本当にすごい体験を沢山させてもらったんです。
①アメリカに高校一年生で留学に行く
②いろんな大企業の人たちと沢山会う
③外務省で学生グローバルサミットに参加する
④ウィリアム王子に会う
⑤安倍昭恵氏と会う
などなど、、、

学校では絶対できない学びと経験をさせてもらい、もちろん幾らかは成長につながっています。でも②辺りから「参加すること自体」が目的になり、これらのキラキラワードを並べて満足してました。経験を能力と勘違いしていた自分に喝を入れてくれたのが、このプロジェクトでした。
また、これは僕の社会貢献観みたいなものも改めてくれました。(ここが大事な話)
「何かで、社会に貢献したい」みたいな漠然とした信念はTOMODACHIに関わって以降、常にありました。別に親戚が亡くなった訳でもないのに留学などに行かせてもらった僕にとって震災はポジティブなものでしかありません。たまたま東北に住んでいただけで誰かのの社会貢献を享受した僕は「受け取った以上のリターンを社会に還元せねば」という勝手な使命感を、当時から、今も変わらず持っているわけです。だから、参加することが目的になっていても、参加したからにはどの機会もめちゃくちゃ一生懸命取り組みました。きっとカオルさんはその姿を見てくれて、リーダーのお誘いをしてくれたんだと、、、そう理解しています。
何はともあれ、被災地のリアルをそこそこ目の当たりにした13歳(2011当時)のボクが震災で一番悲しかったことは、被災者とそれ以外の人の壁でした。というのも、東北に縁もゆかりもない人がたくさん被災地支援をしてくれましたが、「お前らに被災者の本当の大変さ分からないだろ」とか、「偽善者」みたいな排他的なアレを見かけることがたまーにありました。共感はできないけれど、地元の人たちがなぜそう考えるかなんとなく理解出来ていたので、ネイティブ地方出身者としてシティ(国や大企業みたいなところ)で働いて、そういう壁のあるコミュニティの架け橋にならなきゃと思っていました。
このリーダープロジェクトの頃には、ちょっと賢くなり、キラキラワードの手札も増えていたのですが、そうなると口が立つので、地方創生だの、政治や起業の力でどうこうなど、小手先のそれっぽい話ができるようになっていました。でも、これでは経験や知識は優秀なみんなとやり合うためだけのツールになってしまってるなとも、この時やっと思えるようになってきたのです。
純粋に社会貢献したいと思っていた時の僕にとって「社会」は自分を含めた周囲の環境の事だったのに、徐々にそれが「自分と切り離されて存在する他人の集合」になっていたことを感じ始めました。そういうのが偽善に見えるかもしれないし、ネイティブさを感じられないのかもしれません。
「社会はこうあるべき〜」みたいなクソデカ主語イデオロギーにはしょっちゅうモヤモヤしていましたが、僕も本質的にはそれと変わらない形で、自分自信を形而上の存在にして社会を捉え始めていた事を理解しました。なので、社会貢献とは他人が良いとするアクションや言動ではなく、「自分のいる環境へのポジティブな働きかけ」であって、、、僕が変えるべきは社会じゃなくて自分の行動や気持ちのベクトルじゃん、、、と、恥ずかしながら思ったわけです。
大学生になるとちょっと大人に近づくので、早く周囲に対する効力感が欲しくなってしまいますが、肩書きのために官僚や起業家になるのではなく、自分だからこそできる形で自分のいる社会に関わっていかなきゃなと思い始めました。というのが今回の主旨です。(んじゃお前だからできることって何なんだ?編が始まり、足踏みするのは別な話です。)
こういう意欲だけでも受け取ってくれて、たくさんチャンスを与えてくれた 宇多田カオルさんと、TOMODACHIに関わるきっかけをくれた 吉田智子氏にはとても感謝しています。
大谷 史也 や今野拓人とはその後Red Bullでも共に働き、ロンドンに引っ越す直前にはその二人に加えて 木村 勇人 や 江田 翔太 くんも送別会に来てくれました。

松木耕君には、また別途説明するアートプロジェクトに誘ってもらうなど、TOMODACHIで生まれた付き合いは気づけば長いものとなっています。
こうやって振り返ることで、同じチームだった 加藤 美紀さんや 杉田美優さん は元気かなぁとか、 石井 重成 さんはまだティファニー使ってるかなぁとか思うわけです。 中田慧奈さんがすっごい久々にコメントしてくれたように(嬉しかった)、僕もみんなのFBの投稿は覗いています。

また長くなってしまいましたが、こうやってかなり過ぎ去った近況報告をするのは、自分自身の理解に努めるだけでなく、今僕が友人・知人にできる最大のコミットメントだと思っています(※詳細は9月20日の投稿に記載)。
時間はかかっていますが、頑張っている様子ととりあえず元気なことを報告する、周期のおかしい年賀状のようなものです。
最後に、TOMODACHIのプログラムの多くは「リーダーシッププログラム」と名付けられていました。他者からの評価は置いておいて、僕がリーダーシップに自信を持てる理由は、必ずここにルーツがあります。やっぱり、自信が1番大事。仕事でも、今のロンドン生活でも、ゴリゴリやってこれています。未だに自信少なめな僕にとって、この数少ない自信は強さと活力です。
このアラムナイ・ハイライトは、2025年3月23日にクイン・カリーナとアレックス・ファビスが翻訳したものです。二人は現在TOMODACHI アラムナイ・プログラムのインターンです。