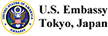ジョンソン・エンド・ジョンソングループとTOMODACHIイニシアチブによる 日米次世代リーダー育成プログラム 「TOMODACHI J&J災害看護研修プログラム」 参加者8名決定

日本のジョンソン・エンド・ジョンソングループ※1(本社:東京都千代田区、以下ジョンソン・エンド・ジョンソン)は、TOMODACHIイニシアチブ※2(以下「TOMODACHI」)とのパートナーシップにより企画・運営する「TOMODACHI J&J災害看護研修プログラム」の参加者8名が決定したことをお知らせします。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、世界共通の行動規範「我が信条(Our Credo)」に掲げる地域社会に対する責任の取り組みの1つとして、米日カウンシルと東京の米国大使館が主導する官民パートナーシップ「TOMODACHIイニシアチブ」の教育支援を通じた被災地復興支援に賛同し、2015年から2017年までの3年間にわたり、東北の災害医療や看護を専攻する看護師の能力育成を図る『TOMODACHI J&J災害看護研修プログラム』の実施を支援しています。
本プログラムは、東北の災害医療を専攻する看護師の能力育成とリーダーシップの構築を図ることを目的に企画されたプログラムで、①米国でのスタディツアー事前準備、②スタディツアー、③スタディツアー後のシンポジウム開催、という主に3つの活動構成となっています。米国でのスタディツアー事前準備では、米国で災害医療や看護に携わる専門家が来日し、海外の最新事情について講演するほか、参加者に対して米国で行われるスタディツアーのためのセミナーや事前準備をサポートします。スタディツアーの参加者は、2015年8月から2週間にわたり、ニューヨークとワシントンD.C.にある災害医療や看護を専門とする施設や団体、そしてトータルヘルスケアカンパニーとして様々な活動の実績を有するジョンソン・エンド・ジョンソンのグローバル本社(米国ニュージャージー州ニューブランズウィック)を訪問し、災害医療の看護師や専門家と交流します。スタディツアーからの帰国後は、東北地方を中心に国内で複数回のシンポジウムを開催し、参加者が、看護学生や災害医療や看護に関心の高い人たちに対して、今回のプログラムで学んだことを共有し、日本国内の災害医療や看護の更なる発展を目指します。
第一回となる今回は、宮城県から選ばれた日本人の看護学生のうち、厳正なる審査の上、8名が参加者として選出されました。
※1:日本のジョンソン・エンド・ジョンソングループについて
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社(コンシューマー カンパニー、メディカル カンパニー、ビジョンケア カンパニー)、ヤンセンファーマ株式会社で構成
【報道関係者からのお問い合わせ先】
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コンシューマー カンパニー
コミュニケーションズ&パブリックアフェアーズ 担当:佐藤克哉 TEL:03-4411-7188 FAX:03-4411-6190
株式会社オズマピーアール 担当:辻本・浜永 TEL:03-4531-0204 FAX:03-3265-5135
【お客様からのお問い合わせ先】
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コンシューマー カンパニーお客様相談室
フリ-ダイヤル:0120-101110 (月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※祝日除く)
J&J災害看護研修プログラム 参加看護学生紹介
 岩渕阿椰茄(いわぶち あやな)
岩渕阿椰茄(いわぶち あやな)
所属:石巻赤十字看護専門学校 2年
地域:宮城県石巻市
このプログラムを通して災害看護や地域看護など医療における諸問題を学び、グローバルな視点と考えを身につけ、自国へ帰り、医療従事者として活動するとき日本の医療を通して様々な場面で貢献し活躍できる人材になりたいと思い応募しました。世界の医療体制や日本と他国の医療の行い方に違いがあるのか、どのようなものなのか興味があります。将来私は、日本だけでなく、災害の援助を必要としている国々や地域で看護師として働き、そして、今後海外で医療者の一人として貢献したいです。被災地の代表として東日本大震災発生時の様子やどんな活動・生活をしていたか、他国でも同じようなことが起きた場合どういう対策や行動をすればよいか情報を発信したいと思います。
 小野寺奈央(おのでら なお)
小野寺奈央(おのでら なお)
所属:気仙沼市立病院附属看護専門学校 2年
地域:宮城県気仙沼市
東日本大震災で自分自身の体験したこと、そこから感じた人との繋がりや命の大切さ、そこから看護の道を志すようになったこと、震災に対する思いを、復興においてたくさん支援してくれたアメリカで、発信したいです。アメリカの軍隊をはじめ、本当に多くの人々が震災後すぐに被災地に来て、多くの人を救ってくださり、水や食料や物資をたくさん提供していただき、津波で壊滅的な被害を受けた危険を伴う場所での行方不明者の捜索、がれき撤去と、数えきれないほど支援していただき助けていただきました。このプロジェクトで出会う人々と今後の被災地の残りの問題について話し合い、考え、そこから何かに繋げたいと思いました。
まず、アメリカの医療の実態を見たいです。自分の目で医療現場を見て、どのような人がどんな医療を提供されているのかといった具体的な状況を知りたいと思っています。私は地元の病院しか知りませんので、高度な機能を持つ病院ではどのような医療を提供しているのか、使用される機器や環境も自分の目で見たいと思います。さらに、震災後、PTSDに悩み苦しむ人が大勢いました。4年経過する今でも私の父は津波の悪夢を見て苦しんでいますし、同じような人はきっとまだ大勢いると思います。今後も苦しむ人々へのメンタルヘルスケアは重要なため、アメリカで実際に行われているメンタルヘルスケアを見学し、今後自分が看護師になったときに参考になるものを得たいと思っています。
私の狭い視野を広げそこから改めて日本や被災地を見つめ、新しい発見や気づかなかった良さや改善点を見い出し、働きかけていきたいと考えています。
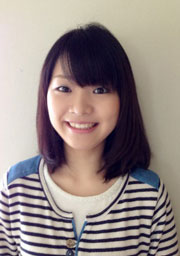 佐藤美輝子(さとう みきこ)
佐藤美輝子(さとう みきこ)
所属:宮城大学看護学部看護学4年
地域:宮城県仙台市
私は宮城大学で看護医療を学び、震災を経験する中で、将来は災害看護に関わりたいと考えています。震災直後はライフラインが途絶え、毎日の生活も大切な人の安否確認もままならない状態でした。そして、2週間後の一通の電話で初めて父が泣き崩れる姿を見ました。その光景は私の脳裏に焼き付き、一生忘れることができません。ずっと心配していた祖母が亡くなったという連絡でした。私は、初めて明日があることが当然だということが覆された瞬間となりました。この経験を通して、「自分のやりたいことは先延ばしにせず行動に移すことや、今、全力を尽くすことが大切だ」と感じるようになりました。
あれからもう4年が経ちますが、祖父は仮設住宅に一人で暮らしています。専門職である保健師や看護師が地域に出向き、祖父を含めた被災者へ直接啓蒙運動を行う様子を見て、現在看護学生として看護を学んでいる身として、災害看護や地域看護について学びたいと感じるようになりました。災害看護研修が行われる米国で、災害から復興したコミュニティへの訪問などのプログラムにとても魅力を感じています。将来は東北の発展を災害復興のモデルケースとして他の地域や海外にも紹介できるように看護師として復興に一生懸命取り組みたいと考えています。
 菅原麻里菜(すがわら まりな)
菅原麻里菜(すがわら まりな)
所属:仙台青葉学院短期大学3年
地域:宮城県仙台市
東日本大震災が起きた頃は高校1年生でした。大学2年生になり、各分野を専門的に学んでいく中で保健師として震災後避難所へ赴き保健活動を行った方のお話を聞く機会があり、住民との繋がりを大切にする地域に根差した活動を展開する保健師と災害看護に強い興味を持つようになりました。その際、看護をする私たちも被災者であることを忘れてはならないということも教えていただきました。私は将来看護職に就いて慣れ親しんだ“ふるさと”である福島で仕事をしたいと思っていますが、原子力発電所の放射線に対する不安が入り交り、どうしても踏み切れない事実があり、公園や学校、駅のいたるところで放射線の測定器を目にするたびにまだ終わっていないのだという気持ちになります。震災によりこころの問題を抱えるようになった人も数多くいます。そうした不安な気持ちをなかなか表出できずにため込んでしまうということは自身の健康を害することにもつながっていくのではないかと考えました。それを防ぐために私たちにできることはいったい何なのでしょうか。看護をする上で大切とされている“人対人の精神”を大切にしながらその人と向き合い、関わっていくことは何よりも大切なことだと信じています。このプログラムに参加して災害看護についての学びや考えをより深いものとし、自分のものだけにするのではなく周りの方々にも伝え、対象の方々のニーズを把握しながらその人に合った行動がとれるようになりたいです。
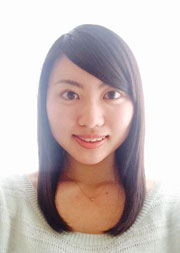 藤沢爽風(ふじさわ そよか)
藤沢爽風(ふじさわ そよか)
所属:宮城大学看護学部看護学科 4年
地域:宮城県仙台市
人は皆それぞれで、年齢が異なれば経験値も考え方も異なります。また、国や文化の違いでも同様のことが言えます。しかし、「死を覚悟する」ことを経験したことのある人はそれほど多くはいません。これは貴重な経験であり、同じことを繰り返さないために災害への普及啓発と自らの経験を伝える必要があります。そして、東日本大震災の経験から伝えたいことは、地域コミュニティ形成の大切さです。
東日本大震災の時、友人の13階にあるマンションにいたら激しい揺れに襲われ、人生で初めて死を覚悟しました。「上と下の階に潰されて、死んでしまうのだ」と思いました。余震の恐怖と戦っていた時に管理人が、「外に出なさい」と階段を駆け上がり呼びに来てくださいました。今回の大震災では、津波で多くの方が命を落としました。地域で呼びかけ、全員で力を合わせ逃げていたらもう少し助かったかもしれない、という思いが私にはあります。震災当日は、自宅に帰れず消防署に一泊したが自宅近くの海に「200~300人の遺体」との言葉をラジオから聞き、家族とも連絡が取れなかったときには、「家族全員の死」をその時覚悟しました。このような「自他共に死を覚悟する」思いを多くの人に抱いてほしくありません。だから私は、この災害看護プログラムに参加し日本のやり方だけでなく国際的な災害に対する考え方を身につけ、今後国際的にどのように災害と向き合っていくべきなのかを考えたいと強く思いました。
将来は、宮城県で保健師として経験を積みその後は青年海外協力隊として活躍したいと考えています。プログラムに参加することにより国際的な立場で災害看護と地域看護の学びを深めることができると確信しています。私は被災した地域で保健師として働くことに意義があると考えていて、国際の場で震災のことを話す際自らの経験と併せて震災後の被災地と被災者の心・身体の現状を伝えることができると考えています。
 星いくみ(ほし いくみ)
星いくみ(ほし いくみ)
所属:仙台徳州看護専門学校
地域:宮城県仙台市
東日本大震災を経験して災害看護に携わりたいと強く思いました。四年前になりますが、私はあの日のことを鮮明に覚えています。震災発生から数日間は、自分の町の状態しか分かりませんでしたが、後々、新聞で伝えられる写真やラジオで流れるニュースでこの震災の大きさを知りました。数か月経ち、震災に関連した特集番組が多く流れ始め、そこで目に留まったのは、命を救おうと懸命に働いている医師や看護師、自衛隊の方々の姿でした。他にも、私たちの知らないところで海外からのボランティアが多く来てくれていたと知り、震災中でもきちんとした生活が送れたのはこのような方々がいたからだと気づき、私も災害時には、最前線で看護師として支えたいと強く憧れを抱いたと同時に、実際に自分が震災を経験したからこそ、少しでも、被災した方々の心に寄り添った看護をさせていただけるのではないかと思いました。私は災害が発生した時には、国内外関わらず最前線に赴き、人命救助に携わりたいと思っています。そのために、いま、多くのことを学び、吸収することだと考えました。アメリカの災害医療・看護をこの目で見て学びたいと強く思いました。
 三浦万里(みうら まり)
三浦万里(みうら まり)
所属:国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校
地域:宮城県仙台市
私は将来、国際的に活躍する助産師になることを志します。2011年3月に東日本大震災という恐ろしい災害が発生し、ライフラインが途絶えて、寒さに震えながら真っ暗な中で家族と身を寄せ合って眠ったことは今も鮮明に覚えています。やっとテレビが映るようになって、目に入ってきたのは恐ろしい津波の映像と、変わり果てた沿岸の町の姿でした。人々は不安や恐怖ややり場のない怒りを抱えながら、避難所で打ちひしがれている様子が報道されていました。何も助けになれない自分自身に無力感を感じ、自分にも何できることをやりたいと考えるようになりました。そんな中で、あるテレビ番組の報道で、震災の日に生まれた新しい命と、それを支えた助産師についての内容が取り挙げられていました。分娩時という緊張感要する場面で、分娩時の器具が倒れないように抑えながら、産婦と赤ちゃんの命を守った助産師の姿に、強く胸を打たれました。また、他にもさまざまな避難所を回って、妊婦に保健指導や衛生面のケア、赤ちゃんのいる家族に物品の工夫を伝えたりしている様子を見て、災害時にも守るべき新しい命はあるのだと気づきました。災害時にこそ医療の力が問われるのだと思いました。助産師としてエキスパートとして、自分の持てる力を最大限発揮したいと考えています。そのためには日本の災害看護を内側からだけでなく、海外の進んだ分野からの学びを通して見つめ、広い視野を持てるようになりたいと考えています。将来的には国際的に助産師として働き、身につけたことを地域の人たちに還元していきたいです。
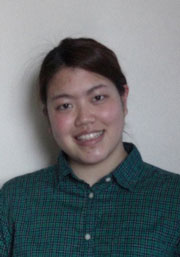 宮川菜津美(みやかわ なつみ)
宮川菜津美(みやかわ なつみ)
所属:石巻赤十字看護専門学科2年
地域:宮城県石巻市
東日本大震災の時は、家族は無事だったが、兄は人工呼吸器で生きているので、父と母は電気を求めて走り回った。避難所は卒業したばかりの中学校だった為、私は避難所でできることをひたすら行いました。「ここをいちばんよく知っているのは私たちなんだ。」と同級生の仲間たちと活動しました。水を運んだり、トイレの掃除もしましたし、笑顔で食事を配り、おじいちゃんおばあちゃんに寄り添いました。「自分だけじゃない。今はみんなが被災者なんだ。」ということがいろんな人の背中を押したのだと思います。思いは繋がっていくものです。伝える気持ちと受け取る気持ちがあれば、言葉が通じなかったとしても感じることはできます。今度は私が誰かの応援に行き、支えたいと強く思いました。この災害看護研修プログラムの経験は、みんなのものであると思います。みんなの代表としていくだけで、学びを次に“繋げる”力が必要です。今はまだ、私の目の前で起きた震災のことやメディアで大きく取り上げられた震災のことしか分からないけれど、勉強してより多くの人の思いを感じて、日本だけでなく、世界の人に届けたいと思います。
将来、赤十字で看護師として働くのか、JICAとして発展途上国の人を支えに行くのか、子供たちに健康を伝える仕事に就くのかまだはっきりしないけれど、今回のプログラムが何かきっかけになることを願っています。アメリカにいる私と同じ気持ちで交流を図ろうと思ってくれている人たちと時間を共有し、よりよい世界を目指す1人として、できることを探し、アクションを起こしていける人間になりたいです。